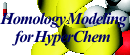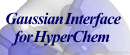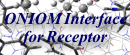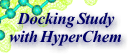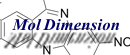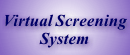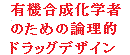![]()
ナチュラル自然結合軌道解析(NBO解析)
有機化学反応における重要未解決問題である反応面立体選択性の本質的原理の解明に成功 (プレスリリース)
Motonori Tsuji. Geometrical Dependence of the Highest Occupied Molecular Orbital in Bicyclic Systems: π Facial Stereoselectivity of Bicyclic and Tricyclic Olefins. Asian J. Org. Chem., 2015, 4, 659-673.
【背景と成果】
速度論支配の有機化学反応において、試薬との反応が反応点に対してどの方向から優先的に起こるか、という問題は立体選択性問題として知られており、反応点の周囲の立体的条件が等価なケースでも一般に立体選択性が生じる。
これまでに反応面立体選択性に関する多くの理論や仮説が提唱されている。立体的に小さい置換基の側から起こる反応が優先される「クラム則」、クラム側に遷移状態の安定性を考慮した「フェルキンモデル」、それに軌道論を導入した「フェルキン−アーンモデル」、遷移状態における超共役効果を考慮した「シープラックモデル」は代表的な反応面選択性モデルとして知られている。しかしながら、これらモデルで説明できない例外的な選択性を示す反応が多く、いずれの理論も単独では統一的説明が不可能であり、反応面立体選択性問題は有機化学の歴史上でも最大級の未解決問題であった。
今回、著者は包括的なモデル実験と最先端の計算化学・理論有機化学を駆使し、過去に報告されてきたいずれの実験結果とも矛盾しない理論を提唱し、反応面立体選択性問題の本質的原理の解明に成功した。すなわち、計算化学を用いた解析により、分子構造(幾何学)に応じて特定のσ(シグマ)軌道がスルースペース/スルーボンド軌道相互作用によってフロンティア軌道に混成されることを突きとめた。その結果、軌道リハイブリダイゼーションおよび軌道チルティングによってπ(パイ)軌道の傾きと大きさが試薬が攻撃してくる方向に有利に摂動を受ける。このことが、立体選択性を示す本質的な原理であると結論した。辻モデルは、1981年にノーベル化学賞を受賞した福井謙一博士のフロンティア軌道理論を拡張する大発見として注目に値する。
【今後の期待】
辻モデルを適用すると、遷移状態を考慮することなく、基底状態の軌道混合則だけで反応面の立体選択性を判断することができる。その結果、有機合成化学を駆使する医薬や農薬といった立体選択性を試行錯誤して開発される薬の構造が設計の段階で予測可能となり、基礎有機化学の発展のみならず産業界に対しても大きく寄与するものと期待される。
自然結合軌道(NBO)解析の詳細な実施例は本論文のSupporting Information(doi.org/10.1002/ajoc.201500054)を参照してください。
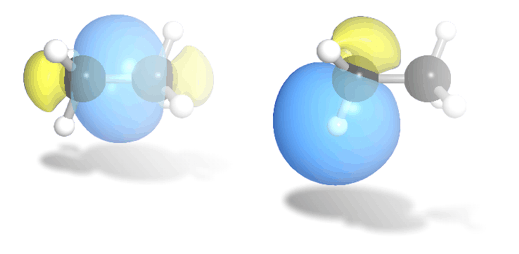
Gaussian Interface for HyperChem